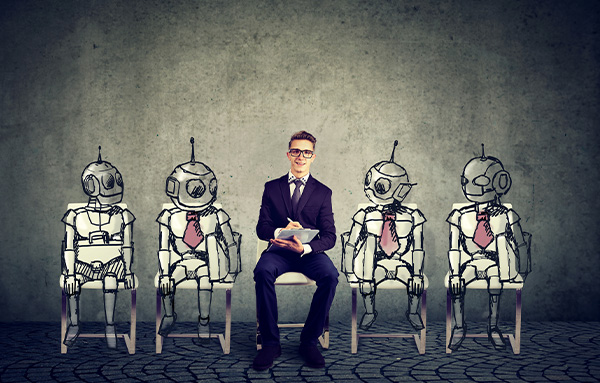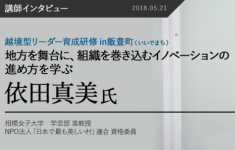-
小西 功二
サイコム・ブレインズ株式会社
ディレクター / シニアコンサルタント
私は、サイコム・ブレインズの営業力強化グループでコンサルタントをしている小西功二と言います。
本日から当社WEBサイト上でコラムを連載していきます。その目的は、お客様(既存のお客様はもちろん、将来のお客様も)に、我々コンサルタントの役割や業務、想いなどを理解していただくことです。その結果、当社コンサルタントをより有効に活用していただき、自社の研修効果をより高めていただければ幸いです。
コラムの内容は、仕事の合間に気軽に読んで、「興味深い」「役に立ちそうだ」と思っていただけるよう、幅広いテーマ(時には脱線も?)を取り上げたいと考えています。
今回は第1回目になりますので、自己紹介を兼ねて、我々コンサルタントの具体的な役割・業務を説明させていただきます。
お客様先でご挨拶すると、「名刺にはコンサルタントって書いてあるけど…?」と聞かれることがあります。ついつい、「営業と同じです」と返答してしまいがちですが、本来は、当社がコンサルタント呼称を使うことへのこだわりがあります。今日はそのこだわりについて説明いたします。
コンサルタントの標準的な業務フローは以下の通りです。
- お客様からの引き合いに応じて、研修ニーズ(組織の課題など)をヒアリングする
- 担当講師のアサインを含めて、ニーズを満たす研修プログラムを企画立案する
- お客様に企画内容をプレゼンテーションする(コンペになることもしばしば)
- 研修プログラムの詳細を設計し、教材を作成する
- 担当講師と事前に打ち合わせ(デリバリートレーニング)する
- 研修当日、運営全般をマネジメントする
- 研修終了後、実施レポートを提出する
コンサルタントがそれぞれのプロセスにどれだけ深く関われるかによって、研修成果は変わってきます。研修の企画フェーズで言えば、上記2では、これまでの経験の蓄積がモノを言いますし、経営やビジネス全般への知識と理解もベースになります。4では、カスタマイズの度合いに応じて、お客様と打ち合わせを重ねたり、場合によってはお客様の営業パーソンに同行して、営業現場の実態を調査したりすることもあります。また、研修成果を可視化するために、あらかじめ受講者のKPI(Key Performance Indicator:管理指標)を設定しておくこともあります。
一方、研修実施フェーズで言えば、6では、受講者の反応を確かめながら、その場で講師のデリバリー(受講者への研修内容の伝え方)に注文をつけたり、場合によってはプログラム内容を急きょ組み直したりすることもあります。また、7では、研修を通じて垣間見えた組織の課題についての仮説をレポーティングすることもあります。それをもとにお客様とディスカッションし、さらなる研修企画につながることも少なからずあります。
繰り返しになりますが、コンサルタントがそれぞれのプロセスにどれだけ深く関われるかによって、研修成果は変わってきます。営業としての機能だけであれば1,2,3にとどまりますが、コンサルタントはそれも含めた研修企画・実施全般について、力量が問われます。当社が、「営業パーソン」ではなく、「コンサルタント」呼称を使用している所以です。自身の反省も込めてあらためて言うと、コンサルタントはお客様の期待に応え、できれば期待を上回れるように、日々研鑽を積むことが求められるのです。
次回は、研修における講師とコンサルタントの役割分担についてお話しいたします。