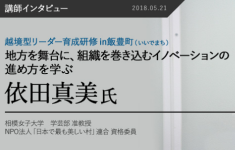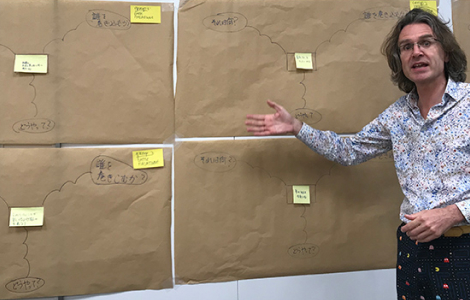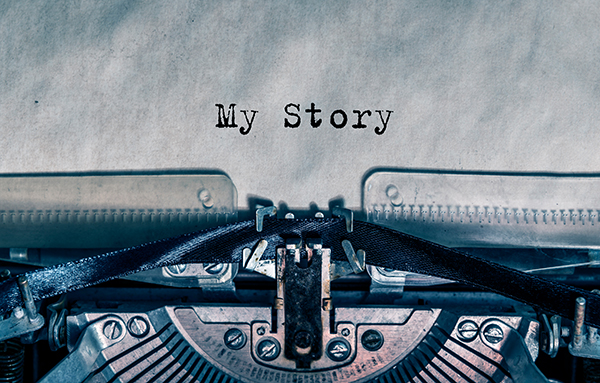-
太田 由紀
サイコム・ブレインズ株式会社
ファウンダー / プログラムディレクター 専任講師

「多様な人材を活かすことで競争優位に立つ」「人材の多様性がイノベーションを生む」――ダイバーシティ推進、あるいはダイバーシティ・マネジメントの説明として、このようなメッセージが発信されています。しかし、このような説明を自分の身の回りで起こる事象として、具体的にイメージできる人は果たしてどれだけいるでしょうか。女性活躍推進だけでなく、LGBTやシニア世代の活用など、様々なトピックが日々アップデートされる中で、自社の経営に資するダイバーシティとは何か、その本質をあらためて考える必要があるのではないでしょうか。今回は、技術経営を専門としながらダイバーシティの領域でも積極的な発信をされている、早稲田大学ビジネススクールの長内厚教授にお話を伺います。

早稲田大学 大学院経営管理研究科(早稲田大学ビジネススクール)教授
1972年東京都小金井市生まれ。1997年、京都大学経済学部経済学科卒業後、ソニー株式会社入社。入社以来、テレビ事業本部で商品企画業務に従事。同社の薄型テレビ事業立ち上げ、ネットワークサーバ等映像関連商品の商品企画、技術企画を担当。ソニーユニバーシティ(社内大学)と筑波大学大学院ビジネス科学研究科(ビジネススクール)で戦略論、組織論を学びながら、新規事業部門の事業本部長付商品戦略担当を務める。2004~2007年に業務留学として京都大学大学院経済学研究科にてイノベーションマネジメントを研究。2007年に博士(経済学)取得後、ソニーの上司のバックアップもあり、研究者に転身。同年、神戸大学経済経営研究所准教授着任。2011年、早稲田大学商学学術院准教授着任。早稲田大学IT戦略研究所研究員、早稲田大学台湾研究所研究員兼任。これまで組織学会評議員、ソニー株式会社外部アドバイザー、台湾奇美実業グループ新視代科技顧問、ハウス食品中央研究所顧問、公益財団法人日本台湾交流協会日台ビジネスアライアンス委員などを歴任。現在、ビジネスブレークスルー大学客員教授、九州大学ビジネススクール非常勤講師、国際戦略経営研究学会理事などを務める。2016年より現職。
研究のスタートから、ダイバーシティの概念が自然と頭の中にあった

- 技術経営がご専門で、日本企業による製品開発・イノベーションに関する問題提起を新聞やウェブメディアで積極的に発信している長内先生ですが、何度かお会いしてお話を伺ったところ、ダイバーシティ経営にもご関心をお持ちなんですね。先日もサイコム・ブレインズが行ったアンケート調査「職場のジェネレーションギャップと無意識の偏見」にも監修という形でご協力をいただきました。そもそも長内先生がダイバーシティに関心を持つようになったきっかけを教えていただけますか?

- イノベーションで一番大きな議論になるのは、イノベーションが非連続なときなんです。イノベーションの99%はインクリメンタル、つまり今までの蓄積の上に何かを積み上げていく形が中心なのですが、何か大きな環境変化があったときに、大企業があたふたしてしまう。失敗してしまう。いわゆる「イノベーションのジレンマ」ですね。ではなぜ大企業が失敗するのか。さまざまな理由がありますが、その多くは今までの成功体験に驕りがある、そうでなくても今までのやり方が当たり前になってしまうんです。

- いわゆるドミナント・デザイン、イノベーションを繰り返すうちに、最初は個性的だったものがみんな同じようなものに固定化されていく、ということですね。

-
ドミナント・デザインが形成されて、仕事もそれに向けて効率化されていく。効率化とは無駄をなくすことですから、余計なことをしなくなる、新しいやり方に対応できなくなる、ということなんです。私自身、ソニーではテレビ事業部にいたのですが、ソニーの場合はブラウン管テレビで大成功したときの体験があって、フラットパネルの時代なってもそれが足を引っ張っていました。
「じゃあ、それってどういうことなの?」というのは、実務の皮膚感覚としてはあったのですが、それを一社員が主張してもなかなか聞いてもらえない。であればきちんと理論的な背景を身につけて、研究者の立場から変えていこう、ということで大学の研究者になったところもあります。その時に何よりも重要だったのは、今までの合理化された狭い仕事のやり方を変えて、様々な意見・アイデアを取り入れていこう、多様性を認めていこう、という方にシフトしていきたい。なので、僕が技術経営の研究を始めるときには、もう自然とダイバーシティの概念が頭の中にあったんです。