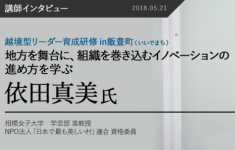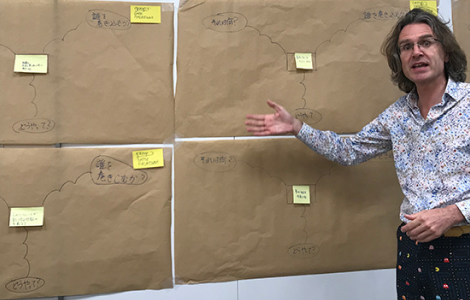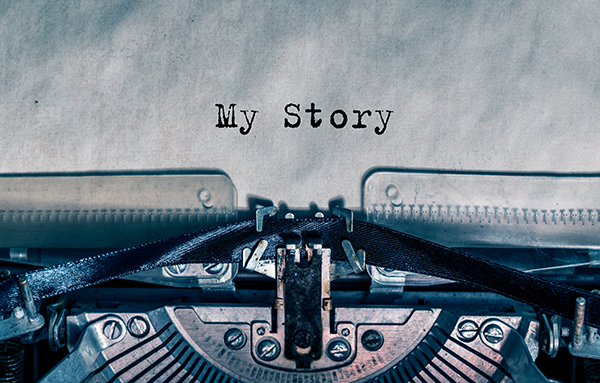-
西田 忠康
サイコム・ブレインズ株式会社
ファウンダー 代表取締役社長

どのような企業であっても、市場の縮小や競争の激化、あるいは「破壊的イノベーション」の到来による市場ルールの一新など、環境変化の影響から免れることはできません。それは経営資源において有利に立つ大企業も例外ではありません。組織の中にある様々な制約を乗り越えながら、常に新しいビジネス機会を追求する人と組織のあり方(コーポレート・アントレプレナーシップ)が、これまで以上に強く求められています。
革新的な製品やサービスの開発、新たなビジネスモデルの創造において、大きな組織だからこそ抱える課題は何か。今回はマサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院教授のマイケル・クスマノ氏、そして日系大手企業でR&D、事業部門、IT戦略など、様々な領域でご活躍されている方々による座談会の模様をお伝えします。
-

- マイケル・クスマノ 氏
- マサチューセッツ工科大学
スローン経営大学院 教授
東京理科大学 特任副学長
-

- 小山 正人 氏
- 株式会社東芝
研究開発センター
LSI基盤技術ラボラトリー 室長
-

- 豊嶋 哲也 氏
- 日本ゼオン株式会社
執行役員
高機能樹脂・部材事業部
事業部長
-

- 芳賀 恒之 氏
- 日本電信電話株式会社
NTT先端集積デバイス研究所
所長
-

- 増田 佳正 氏
- 武田薬品工業株式会社
エンタープライズ・アーキテクチャー
担当マネージャー
-

- 西田 忠康(進行役)
- サイコム・ブレインズ株式会社
代表取締役社長
R&D、事業部、IT部門 …大企業のイノベーションにおける課題

Michael A. Cusumano
マサチューセッツ工科大学(MIT) スローン経営大学院 教授 / 東京理科大学 特任副学長 MITスローン経営大学院および工学部教授。ビジネス戦略やテクノロジー・マネジメントに関する世界的権威。主にハイテク産業分野における数々の大手企業のコンサルタントを努め、数社の役員を歴任。2016年4月より1年間、東京理科大学の副学長として同学のSchool Of Businessを構築。著書に”The Business of Software”(ソフトウエア企業の競争戦略)、”Staying Power”(君臨する企業の「6つの法則」)など。最新作は”Strategy Rules: Five Timeless Lessons from Bill Gates, Andy Grove, and Steve Jobs”(ストラテジー・ルールズ – ゲイツ、グローブ、ジョブズから学ぶ戦略的思考のガイドライン)。
-

-
サイコム・ブレインズの西田です。
本日は東京理科大学のクスマノ教授の研究室にお邪魔して、座談会という形で皆さんのお話をお聞きしたいと思います。2003年から2009年まで、MITではクスマノ教授をディレクターとして日本人を対象とした技術経営(MOT)人材育成プログラムを実施していました。サイコム・ブレインズは日本側で受講者の募集や準備プログラムを提供していて、本日それぞれの企業からお越しいただいた4人の方も、このプログラムの受講者でした。
今回は「コーポレート・アントレプレナーシップ」というテーマで皆さんとお話をしたいのですが、まずは皆さんから自己紹介を兼ねて、現在取り組んでいること、今日のテーマに限らず抱えている課題などがあればお聞きしたいと思います。
-

-
マサチューセッツ工科大学のマイケル・クスマノです。
東京理科大では4年前から顧問をしていますが、昨年の4月から特任副学長として仕事をしています。特任副学長としての仕事は、大きくいうと3つあります。一つは経営学部を作り直すこと。埼玉の久喜にあったキャンパスを去年の4月に神楽坂に移転して、学生の数も倍の500人にしました。アントレプレナーシップの授業も必修科目にしました。2つ目は、MOTのプログラムを作り直すことです。カリキュラムを完全に作り直して、2018年の4月からスタートしますが、今日のテーマでもあるコーポレート・アントレプレナーシップを重要な柱として位置づけています。3つ目は「MIT REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration Program)」です。これはMITが世界中で実施している「それぞれの地域に合った起業家育成システムを構築する」ことを目的としたプログラムです。現在その第3期として、日本を含む8カ国が参加しているのですが、企業や行政機関などで構成される日本チームのメンバーとして、教育機関である理科大も研究やネットワーキング活動の場として関わっています。
-

-
NTTの芳賀です。
MITのプログラムに参加したのは2008年でした。もともとの専門は半導体の微細加工でしたが、当時はまったく別の分野で10人ほどのグループのリーダーをしていました。専門外の分野を引っ張っていくにはどうしたらよいか、どうやってイノベーションの足がかりをつくっていくかを考えながら仕事をしていたときに、MITで勉強させていただきました。現在は先端集積デバイス研究所という、電子デバイスや光デバイスの研究所のマネジメントをしています。NTTをとりまく環境もだいぶ変化していて、ここ10年間くらいを見ても、通信料による収入が4分の1以下になって、システムインテグレーションとか、海外でのビジネスで収入を得る会社へと変わってきています。我々の研究所としても通信だけではなく、ビジネス・パートナーとコラボレーションしながら、新しいビジネスモデルを生み出していく方向に舵を切っているところです。
-

-
武田薬品の増田です。
MITのプログラムに参加したのは2008年で、当時は前職のIBMで仕事をしていました。現在は「エンタープライズ・アーキテクチャー」といって、企業全体の業務とシステムの最適化を図るためのITアーキテクチャー計画・将来像の策定とIT戦略との整合、戦略をグローバルで展開するためのマネジメントをしています。「デジタル・トランスフォーメーション」あるいは「デジタル変革」という言葉がありますが、武田薬品もITを活用して健康・医療分野で新しい事業を生み出す「デジタルヘルス」の領域に参入しようとしています。デジタル変革は、IT業界の中では今までで一番大きな波だと思います。それは技術的なことだけじゃなく組織的にも大きな変革で、IT部門の人たちがビジネス部門へ移っていく流れでもあるからです。それにどのようにして対応していくのかが、今後の課題であると感じています。
-

-
日本ゼオンの豊嶋です。
高機能樹脂やその成形品を扱う事業部のマネジメントをしています。私がMITのプログラムに参加したのは2005年で、大雪のボストンで2週間、缶詰になって勉強した記憶が懐かしいです。当時は「シクロオレフィンポリマー」という、新しい樹脂を利用した加工製品の事業が立ち上がった初期の頃で、私は研究所で開発チームのリーダーをしていました。シクロオレフィンポリマーが上市されたのが、1992年頃。既に25年が経っていますが、いまだに社内では「新規事業」と呼ばれているくらい、素材産業はすごくゆっくりとした時間の中で生きてきたんですね。ところが、ちょうど私が入社した頃に、かつては樹脂をそのままお客様に売っていたところを、我々自身でフィルムに加工して売るようになりました。加工したフィルムはスマホのタッチパネルやテレビの液晶ディスプレイなどに使われるのですが、当時はスマホではなくガラケーの時代。テレビも液晶ではなくまだブラウン管でした。その後は皆さんご存知の通り、いわゆる「破壊的なイノベーション」によって、どんどんデバイスが置き換わっていく中に身を置いてきました。
2011年に研究所から事業部に異動して、いわゆる商売のことを考える立場になりましたが、危機感を持ちながら新しい事業を展開していくことの難しさを日々実感しています。
-

-
東芝の小山です。
MITのプログラムは2009年に参加しました。私の場合はわずか一週間の滞在で、ボストンの街を楽しむ余裕もなく一生懸命学んでいたことを思い出します。当時、研究員に2年間くらい様々な経験をさせる「流動研究員」という制度があって、私は企画や戦略に関わる仕事、あとは研究所のトップがいろいろなところで話をするための調査や資料づくりといったことも経験しました。そのような中でMITで学んだことによって、経営的な言葉に対するリテラシーが上がったことが一番の成果でした。その後、研究の現場に戻ってNAND型フラッシュメモリの先端開発を進めてきました。私がいるのはコーポレートの研究所なので、今すぐのことというより3年から5年先のことを考えて研究をしています。競合相手は非常にコスト競争力のあるアジアの会社ですので、研究所として新しいことをやると同時に、「いかに安く作るか」についてあらかじめ考えておかなければなりません。そういった意味で、現在の悩みというか関心は「研究所からどのようにして競争力を生み出していくか」ということですね。
From Laboratory to Business … 研究所から競争力を生み出す

東京理科大学経営学部 マイケル・クスマノ教授研究室にて
-

- まずは「研究所から競争力を」という、小山さんのお話から掘り下げてみようと思います。小山さんが研究されているフラッシュメモリは、技術の進化が非常に速くて、価格が安くなるのも速い。確かにコスト競争は激しそうですね。
-

-
そうですね。我々はビットコスト(記憶容量あたりの価格)という言葉を使うのですが、それが一年で数10%も下がります。先ほど豊嶋さんから素材産業の時間の流れ方を聞いて非常に驚いたのですが、我々の場合は「一年で一世代」という感じです。研究が全然追いつかないくらいのスピードですが、グローバルな競争の中でステップダウンしたらもう終わりです。
そのような厳しい競争の中だと、基本的には自社で技術を囲い込んでやっていきたいという気持ちが強くなるのですが、やはりそれではなかなか難しい。先ほどお話した流動研究員だったときに、いろんな大学や国家プロジェクトの現場にいった経験から、やはりオープン・イノベーションというか、外とつながっていくことに興味があります。実際のところどのようにしたらよいのか、日々悩んでいるところです。
-

- 難しい問題ですね。オープン・イノベーションができたとしても、東芝独自の技術にならないし、差別化もできない。
-

- 技術をあずかっている立場からすると、非常に少ない人数で研究開発しても、低コストで競争力のある製品というのは生まれにくいと思うことは多いですね。

小山 正人 氏
(株式会社東芝 研究開発センター LSI基盤技術ラボラトリー 室長)
-

- オープン・イノベーションといえば、NTTさんはR & Dだけでなく、営業部門も様々な業界の企業とアライアンスを組んでビジネスを作ったり、その中で自社の通信サービスを提案する取り組みが盛んですね。
-

- そうですね。NTTの場合は組織が大き過ぎて、これまでも何かしようとするといろいろな方面から反発を食らってしまうことは何度もありました。今は黒子に徹するという策を取っていますので、すごくクレバーな戦略だと思っています。
-

- 日本ゼオンさんの場合は、樹脂という素材を売るだけではなく、それをフィルムに加工して部材として売るというモデルを取り入れたことで、競争力を生み出したといえるのではないでしょうか。
-

- それまでは「これを御社で活かして使ってください」と言う立場だったところが、我々から使い方を提案できるようになったという意味では、競争力を生み出せたのだと思います。売上や利益の面でも、事業部門の中で無視できない大きさにまで成長しました。そのような中で今後やっていきたいのは、プロトタイプを作って、実際に動いているのをお客様に見てもいながら新しい製品を作ることですね。
-

- 情報システムの開発でも、これまではユーザーの要望を聞いて作っていたところが、プロトタイプを作って、ユーザーさんの意見を聞きながらアジャストして、徐々に市場に出していく方法に変わってきています。ただモノを作って売るという従来の手法が通用しなくなったという点では同じですね。
-

- ただこのフィルムに関しては、あまねく世の中に広まってしまったその次をどうするかが課題です。テレビの次にスマホが出てきたところまではよかったのですが、スマホのライフサイクルもそろそろ見えてきています。今後我々が作るものがどのように貢献できるのか、暗中模索の状態ですね。
-

- たとえば部材だけではなくモデルまで作るとか、もっと上位のところから取り組むことで、次のものが生まれるかもしれない。でもそうなると、パートナーやお客さんと競争になってしまうんですよね。簡単じゃないですね。
-

- 光学フィルムの分野ではなかなか難しいと思っていて、よほどのイノベーション、新しい提案がないとお客様とコンフリクトしてしまいます。やはり新しいアプリケーションにおいてそういったものを作っていかなければならないと思います。
-

-
部品を作ることにおいて日本企業は進んでいますが、産業全体、ビジネスモデルを作るとなると弱いと思います。少なくとも日本の会社は研究を一生懸命やっていて、それはすごくいいことだとは思いますが、あまり新しい事業にはならない。理由の一つは、企業と大学があまり協力しないことです。大学で技術者に対してビジネス面での教育が不足している点も理由だと思います。
もう一つ、日本の企業の思考がより短期的になっていると思います。毎月の業績を見て先月と比べてどうなっているか、一年前と比べてどうかとかは管理するけど、あまり長期的には考えない。30~40年前はそうではなかったと思うんですよ。私が日本に初めて来たのが40年前で、日本の会社について研究を始めたのが35年前くらいですが、当時の印象はまだ富国強兵というか、日本の将来のために働こうという気持ちがあって、会社側も長期的なプロジェクトをやろうとしていたように思います。
-

- 日本企業がもともと投資家との対話とかIRが得意ではなかったのに加えて、短期的な業績で会社が評価される世の中になってしまった。経営者も日々の業績を出さないとダメだというふうに変わってきてしまった、というのは強く感じますね。
-

- 問題は、そういう短期的な考えだけにとらわれると、業績が落ちて今後の見通しもつかない状況になってしまうと、そこから回復することが難しくなる。負のスパイラルです。もっと長期的な投資をしないとダメですよね。